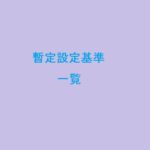パイロットのライセンスまとめの記事です。
エアラインパイロットの機長になるまでには様々なライセンスを取得していくわけですがそのライセンスについてまとめました。
パイロットのライセンスについては航空法の第4章「航空従事者(第22~36条)」に規定があります。
目次
エアラインパイロットが持っているライセンス
エアラインパイロットの機長が持っているライセンスは以下の通りです。
・第一種航空身体検査証明
・航空無線通信士
エアラインの副操縦士が持っているライセンスは以下の通りです。
(もしくは准定期運送用操縦士)
・第一種航空身体検査証明
・航空無線通信士
それぞれの資格の業務範囲は航空法第28条に規定されています。
事業用操縦士
事業用操縦士は航空大学校で取得可能な免許で、パイロットとして仕事をしていく上では最もベーシックな免許です。
ライセンスには必ず業務範囲というものがあり、各技能証明の業務範囲は航空法第28条に定められています。
事業用操縦士の業務範囲(法第28条関連)
業務範囲は以下の通りです。
航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。
一 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
二 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
三 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
四 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
五 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機にあつては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。(航空法から引用)
エアラインでの副操縦士の業務は第4号「機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと」にあたります。
計器飛行証明(法34条)
計器飛行証明も航空大学校で取得できます。
計器飛行証明については航空法第34条第1項に規定されています。
第34条
定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。(以下略)
(航空法第34条第1項から抜粋)
この条文は一見すると定期運送用操縦士、准定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士は計器飛行証明を持っていなければ計器飛行等を行ってはならないという意味かと誤解しそうですが、そのような意味ではありません。
法律の文の決まり事として「若しくは」と「又は」は使用方法が違います。詳しくは調べてみてください。
この条文では「定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士」と「事業用操縦士若しくは自家用操縦士」をかたまりとして、それらを「又は」で並べています。
又は
[事業用操縦士若しくは自家用操縦士]の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。
つまり、事業用操縦士や自家用操縦士が計器飛行等を行うためには計器飛行証明のライセンスが必要ですが、定期運送用操縦士・准定期運送用操縦士の資格を持っていれば計器飛行証明が無くても計器飛行等を行うことができます。
定期運送用操縦士
定期運送用操縦士の業務範囲(法第28条関連)
定期運送用操縦士の業務範囲は以下の通りです。
航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。
一 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
二 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。
三 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であつて、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。(航空法から引用)
第2号の航空運送事業の構造上操縦のために2人を要するものというのがボーイングやエアバスなどのいわゆる旅客機のことです。
第3号の「特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの」とはなんでしょうか?
それは基本的には構造上1人で操縦できる航空機であっても、例えば計器飛行方式(IFR)で飛行する場合は操縦に2人を要すると飛行規程に定められている航空機の事です。
しかし、実はこの定期運送用操縦士の資格を持っているだけでは航空運送事業の機長として業務をすることはできません。
定期運送用操縦士の資格を持っていることに加え、航空法72条の機長認定を受けなければなりません。
定期運送用操縦士の受験要件(法第26条関連)
誰でも受けられるわけではなく一定の要件を満たす必要があります。
ここではエアラインの飛行機に限定して簡単に説明します。
要件としては「1500時間の飛行時間」が必要です。
その1500時間の中に、
・200時間以上の野外飛行
・100時間以上の夜間飛行
・75時間以上の計器飛行
が含まれていることが要件です。
そしてさらに機長時間として100時間以上の野外飛行を含む計250時間以上の飛行経験も必要となっています。
この「機長時間」ですが、エアラインの副操縦士として働いていて「機長ができない段階でどうやって機長時間を積むのか?」という問題があると思います。
エアラインで副操縦士として飛びながら「機長見習い業務」をすることで、その時間も機長時間として加算することができます。(加算は上限あり)
准定期運送用操縦士
准定期運送用操縦士の業務範囲(法第28条関連)
准定期運送用操縦士の業務範囲は以下の通りです。
航空機に乗り組んで次に掲げる行為を行うこと。
一 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。
二 機長以外の操縦者として、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。(航空法から引用)
定期運送用操縦士は事業用操縦士が行うことができる行為は行うことができますが、准定期運送用操縦士は行えません。
したがって、准定期運送用操縦士は構造上一人の操縦者で操縦することができる航空機を操縦できません。
エアラインの副操縦士専門の資格です。
第一種航空身体検査証明(法31,32条)
航空身体検査については航空法第31条に規定されています。
航空機のライセンスを持っていてもこれが無いと何も操縦できないのでパイロットにとって一番大事なものです。
ただ一般的な健康であることではなく、航空業務に支障がないことが重要です。
航空法第32条(具体的には航空法施行規則63条の3)には身体検査の有効期限について規定されています。
基本的に有効期限は1年間ですが、「航空運送事業で1人で操縦する場合、かつ40歳以上」と「航空運送事業で2人で操縦する場合、かつ60歳以上の人」は6ヵ月です。
航空無線通信士
無線の資格が別に必要ですが、これは簡単に取ることができます。
ほとんどの人が航空大学校入学前の大学生の時に取っています。
1度取ると有効期限はなく、一生有効です。
日本でパイロットのライセンスを取る方法
では日本でどのようにライセンスを取ればよいのでしょうか。日本でライセンスを取るには大きく分けて2通りの取り方があります。
航空法第29条(試験の実施)に規定されています。
一つ目は飛行要件を満たして自分で試験を受けるやり方です。
第29条
国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
(航空法から引用)
上記の通り、航空法で定める要件を満たしていれば技能証明を受けるための申請をすることができ、申請があれば国は試験をしなければなりません。
試験の結果、基準を満たしていれば技能証明をもらえます。
もう一つは航空大学校や指定航空従事者養成施設の課程を修了する方法です。
法29条4項
国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。
(航空法から引用)
航空大学校や指定航空従事者養成施設ではそれぞれ規程に則って訓練・審査が行われます。
そのカリキュラムを修了することで技能証明がもらえます。
通常は国土交通省の試験官が試験を実施しますが、指定航空従事者養成施設(例えば某大手航空会社)では、その施設の教官・技能審査員により訓練と審査を行い、その施設の訓練生に技能証明を取らせることができます。
大手航空会社の自社養成パイロットはそのようにしてライセンスを取ります。
どこの訓練施設でも指定航空従事者養成施設になれるわけではなく、定められた基準を満たしている必要があります。
まとめ
ライセンス関係は航空法第4章「航空従事者(第22~36条)」に規定があります。
機長は定期運送用操縦士の資格、副操縦士は「事業用操縦士+計器飛行証明」もしくは准定期運送用操縦士の資格が必要です。
それに加えて有効期限内の航空身体検査証明を持っていなければ航空業務を行うことができません。