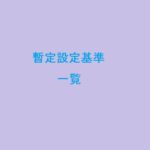パイロットは航空法を勉強するときに、第6章(法第99条まで)まではよく勉強しますが、第7章以降についてはあまり見たことがない人は多いと思います。
航空法の第7章は「航空運送事業等」であり、試験ではほとんど出題されないからです。
航空法第6章までを知っていれば飛行機は飛ばせますし、エアラインパイロットになったとしても自分が航空運送事業を行うわけではありません。
今回はこの航空法第7章についての備忘録です。
航空法第7章には第100条~第125条があります。
目次
航空法第7章の概要
航空法第7章は「航空運送事業等」について書かれています。
内容としては航空運送事業を行うための手続き、基準、運営方法、航空運送事業の安全の確保、航空機使用事業について規定されています。
この法律があるので、個人が勝手に航空会社を立ち上げて勝手に経営することはできません。
第7章の1番初めの法第100条第1項には、航空運送事業を経営するには国土交通大臣の許可が必要だと規定されています。
法第100条
航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(航空法から抜粋引用)
この許可を受けようとする者は定められた事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければなりません。定められた事項の中には、当然ですが事業計画が含まれます。
法第101条では許可基準が定められています。
そして以降の条文でその許可を取るためには何が必要で何をしなければならないかが規定されています。
許可、認可、届け出について
第7章では手続きについて書かれたものが多く、その中でも「許可」「認可」「届け出」という用語が出てきます。
定義が違うのでそれらの言葉を確認しておきましょう。
「許可」とは、基本的に禁止されていることを定められた一定の手続きを踏んで行政が解禁することです。
「認可」とは、行政がお墨付きを与えることです。
「届け出」とは、一方的に必要な書類・資料などを提出することです。
許可と認可の違いがよくわからないと思うので各項目を見ていきましょう。
航空運送事業者が定めるべき項目
①安全管理規程
法第103条の2で規定されています。
安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければなりません。変更するときも同様に届け出が必要です。
②運航規程と整備規程
法第104条で規定されています。
運航規程と整備規程を定めて国土交通大臣の認可を受けなければなりません。変更するときも同様です。
上でも触れましたが、認可とは行政がお墨付きを与える行為です。
「この運航規程と整備規程でOKですよ」という国土交通大臣のお墨付きを得ることが必要です。
③運賃及び料金
法第105条で規定されています。
運賃及び料金を定めて国土交通大臣に届け出なければなりません。運賃及び料金は認可は必要ありません。
また、法第107条の規定により、これは第三者が閲覧できる状態にしておく必要があります。
④運送約款
法第106条で規定されています。
運送約款を定めて国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
また、法第107条の規定により、これは第三者が閲覧できる状態にしておく必要があります。
⑤運航計画
法第107条の2で規定されています。
運航計画を定めて国土交通大臣に届け出なければなりません。
⑥混雑空港使用の許可
法第107条の3に規定されています。
混雑空港を使用する場合は混雑空港ごとに国土交通大臣の許可を取らなければなりません。そしてその許可には有効期限があります。
詳しくは航空法施行規則第219条の2に規定されており、現時点では混雑空港は成田、羽田、関空、伊丹、福岡の5空港となっています。
期限の年数は全て5年となっています。
事業計画等の遵守・変更
法第108条には、事業計画等の遵守について規定されています。
法第108条
本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。
(航空法から抜粋引用)
これは例え、お客様の予約がほとんどなかったとしても、航空会社の都合で勝手に欠航にできないということを規定しています。
また、法第109条の規定により、事業計画を変更するときには国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
安全上の支障を及ぼす事態の報告
航空運送事業を行っていて、安全上の何か支障がある事態が発生した時に航空運送事業者は報告をしなければなりません。
法第111条の4
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
(航空法から引用)
具体的に報告が必要な事項については航空法施行規則第221条の2に定められています。
航空法施行規則第221条の2
法第111条の4の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 法第76条第1項各号に掲げる事故二 法第76条の2に規定する事態三 航空機の航行中に発生した次に掲げる事態イ 航空機の構造が損傷を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は小修理に該当しない場合を除く。)ロ 航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態ハ 非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態ニ 運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態ホ イからニまでに掲げるもののほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態四 前三号に掲げるもののほか、航空機の構造の損傷、非常用の装置の故障、装備品等の誤つた取付けその他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態(航空法施行規則から引用)
一、二号の法第76条は「機長の報告の義務」に関する条文です。
事業改善命令
航空会社に不祥事があったときなどの事業改善命令についての規定も航空法第7章に定められています。
法第112条
国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画又は運航計画を変更すること。二 安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。三 運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。四 航空機又は運航管理施設等を改善すること。五 第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。六 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。(航空法から引用)
航空運送事業者が定めるべき事項の安全管理規程、運航規程、整備規程、運賃及び料金、運送約款、事業計画・運航計画が不適切な場合は国土交通大臣は改めさせるための命令が出せます。
まとめ
航空運送事業をするためには国土交通大臣の許可が必要です。その際に事業計画が必要です。
航空運送事業者がやるべきこととして以下の事があります。
①安全管理規程⇒届け出
②運航規程、整備規程⇒認可
③運賃及び料金⇒届け出
④運送約款⇒認可
⑤運航計画⇒届け出
※混雑空港使用にはさらに許可が必要